新生活への期待が膨らむ一方、「やることが多すぎて何から手をつければいいか分からない…」と不安を感じていませんか?
この記事では、そんなあなたのために必要な準備や手続きを網羅した「やることリスト」を、時系列で徹底解説します。複雑な役所の手続きから電気・ガス・水道といったライフラインの契約、荷造りのコツまで、これ一つで全て解説!
一人暮らしの引っ越し「やること」全体の流れとスケジュール

引っ越しの準備は、段取りが9割です。まずは全体像を把握し、いつ何をすべきかというスケジュール感を掴むことから始めましょう。
まずは全体の流れを把握しよう!引っ越し完了までの5ステップ
一人暮らしの引っ越しは、大きく分けて以下の5つのステップで進みます。自分が今どの段階にいるのかを意識するだけで、落ち着いて準備を進められます。
- 引っ越し1〜2ヶ月前(情報収集・物件決定)
- 新生活の土台を作る最も重要な時期です。住みたいエリアの情報を集め、不動産会社を訪れ、内見を重ねて新居を決定します。同時に、引越し業者の情報収集や不用品の洗い出しも始めましょう。
- 引っ越し1ヶ月前〜2週間前(各種手続き・荷造り開始)
- 具体的なアクションを開始する時期です。引越し業者を決定し、インターネット回線の手続きを進めます。普段使わないものから荷造りを始め、役所での手続き(転出届)もこの時期に済ませておくと安心です。
- 引っ越し2週間前〜前日(最終準備・ライフライン連絡)
- 準備の総仕上げ期間。電気・ガス・水道の停止・開始手続きを完了させ、荷造りを追い込みます。冷蔵庫の水抜きなど、家電の準備も忘れずに行いましょう。
- 引っ越し当日(搬出・搬入・各種立ち会い)
- いよいよ引っ越し当日です。旧居での荷物搬出、新居での搬入に立ち会い、ガスの開栓などライフラインの開通を確認します。
- 引っ越し後(各種手続き・荷解き)
- 新生活のスタートです。役所での転入・転居手続きや運転免許証の住所変更など、期限のある手続きを速やかに行い、少しずつ荷解きを進めていきましょう。
一人暮らしの引っ越しで必須!役所・ライフラインのやることリスト
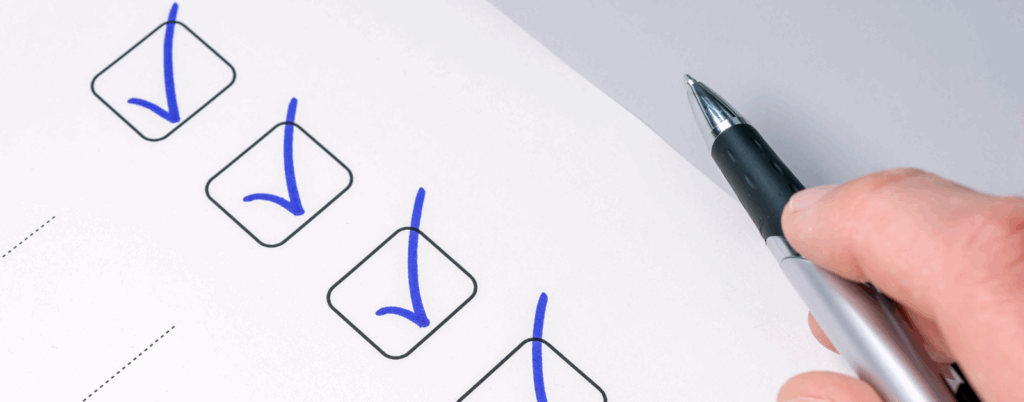
チェックリストで挙げた手続きについて、具体的な方法や注意点を詳しく解説します。「何をどこに持っていけばいいの?」という疑問は、ここで全て解決しましょう。
①旧居・新居の役所でやること(転出届・転入届など)
役所の手続きは期限が定められているものが多く、新生活の基盤となる重要な作業です。
転出届の手続き(他の市区町村へ引っ越す場合)
- いつまでに
- 引っ越し日の14日前〜当日まで
- どこで
- 旧住所の市区町村役場
- 必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(認印でOK、不要な場合も)
- 国民健康保険被保険者証、各種医療証など(該当者のみ)
- ポイント
- 手続きをすると「転出証明書」が発行されます。これは転入届の際に必要なので、絶対に紛失しないようにしましょう。マイナンバーカードがあれば、マイナポータルからオンラインでの提出も可能です。
転入届の手続き(他の市区町村から引っ越した場合)
- いつまでに
- 引っ越し日から14日以内(法律上の義務)
- どこで
- 新住所の市区町村役場
- 必要なもの
- 転出証明書(旧住所の役所で発行されたもの)
- 本人確認書類
- 印鑑
- マイナンバーカード(または通知カード)
転居届の手続き(同じ市区町村内で引っ越す場合)
- いつまでに
- 引っ越し日から14日以内
- どこで
- 現住所の市区町村役場
- 必要なもの:
- 本人確認書類
- 印鑑
- マイナンバーカード(または通知カード)
- 国民健康保険被保険者証など(該当者のみ)
マイナンバーカード(または通知カード)の住所変更
転入届・転居届を提出する際に、必ずマイナンバーカード(または通知カード)を持参し、同時に住所変更手続きを行いましょう。手続きには暗証番号の入力が必要です。
国民健康保険の資格喪失・加入手続き
- 他の市区町村へ引っ越す場合
- 旧住所の役所で資格喪失手続き(転出届と同時)→新住所の役所で加入手続き(転入届と同時)を行います。
- 同じ市区町村内で引っ越す場合
- 転居届と同時に住所変更手続きを行います。
- 実家から独立する場合
- 親の扶養から外れ、自分で国民健康保険に加入するか、就職先の社会保険に加入することになります。事前に親や勤務先に確認しておきましょう。
②ライフライン(電気・ガス・水道)でやること
電気・ガス・水道は、生活に不可欠なライフラインです。連絡漏れは絶対に避けたいところです。
電気の停止・開始手続き
- 連絡のタイミング
- 引っ越し日の1〜2週間前まで
- 連絡先
- 旧居と新居の管轄電力会社
- ポイント
- 最近は電力自由化により、様々な会社から選べます。新居で契約する電力会社を比較検討してみるのも良いでしょう。手続きは各社のWebサイトから24時間申し込めることが多く、電話よりも手軽でおすすめです。新居では、ブレーカーを上げればすぐに電気が使える場合がほとんどです。
ガスの停止・開始手続き
- 連絡のタイミング
- 引っ越し日の1〜2週間前まで
- 連絡先
- 旧居と新居の管轄ガス会社
- ポイント
- ガスは、新居での開栓作業に必ず本人の立ち会いが必要です。引っ越しシーズンは予約が混み合い、希望の時間帯が埋まってしまうことも。「引っ越したのにお風呂に入れない…」という事態を避けるため、物件が決まったらなるべく早く予約しましょう。
水道の停止・開始手続き
- 連絡のタイミング
- 引っ越し日の1〜2週間前まで
- 連絡先
- 旧居と新居の管轄水道局
- ポイント
- 手続き方法は電話、FAX、Webサイトなど自治体によって様々です。新居の玄関や郵便受けに、水道使用開始の申込書が入っていることもあります。
③通信・その他でやることリスト
見落としがちですが、生活の快適さを左右する重要な手続きです。
インターネット回線の手続き
- タイミング
- 物件が決まったら即日!
- ポイント
- 固定回線を引く場合、開通工事が必要になることがあります。特に繁忙期は工事まで1ヶ月以上待つケースも珍しくありません。新生活が始まってもネットが使えない「ネット難民」にならないよう、最優先で手続きを進めましょう。建物によっては工事不要の場合や、備え付けの無料Wi-Fiがある場合もありますので、不動産会社に確認が必要です。
郵便物の転送手続き
- 方法
- 郵便局の窓口にある「転居届」を提出するか、Webサイト「e転居」で手続きします。
- ポイント
- 手続きをすると、旧住所宛の郵便物が1年間、無料で新住所に転送されます。登録から転送開始まで3〜7営業日ほどかかるため、引っ越しの1週間前までには済ませておきましょう。
携帯電話・スマートフォンの住所変更
契約している携帯電話会社のWebサイト(マイページなど)や店舗で手続きします。請求書や重要なお知らせが届かなくなるのを防ぐため、忘れずに行いましょう。
銀行・クレジットカード・保険会社などの住所変更
各社のWebサイト、アプリ、電話、郵送などで手続きします。特にクレジットカードや保険は、住所変更を怠ると重要な書類が届かず、更新カードが受け取れないなどの不利益に繋がる可能性があります。後回しにせず、早めに済ませましょう。
一人暮らしの引っ越し当日にやるべきことリスト
入念に準備をしても、やるべきことはたくさんあります。最後まで気を抜かずに乗り切りましょう。
引っ越し当日の流れと注意点
旧居での作業(荷物搬出の立ち会い、最終清掃)
業者の作業中は、指示を出したり、質問に答えたりするために必ず立ち会います。全ての荷物が運び出されたら、忘れ物がないか各部屋のクローゼットや収納を最終チェックし、感謝の気持ちを込めて簡単な掃除をします。
退去の立ち会い(管理会社・大家さん)
部屋の状態を一緒に確認します。ここで、経年劣化や通常の使用による損耗(貸主負担)と、借主の故意・過失による損傷(借主負担)の切り分けなど、修繕費(原状回復費用)の負担について確認を行うため、非常に重要です。事前に部屋を綺麗にしておくことで、心証が良くなることもあります。確認が終わったら、鍵(スペアキーも忘れずに)を返却します。
新居への移動
公共交通機関や自家用車で移動します。貴重品や「第一陣ボックス」は、自分で運ぶと安心です。
新居での作業(荷物搬入の指示、初期傷のチェックと写真撮影)
新居に到着したら、まず部屋の傷や汚れがないかを入念にチェックします。これは退去時のトラブルを防ぐために最も重要な作業です。
- チェックポイント
- 床の傷やへこみ、壁紙の剥がれや汚れ、水回りのカビ、設備の動作不良など。
- 記録方法
- スマートフォンで日付がわかるように写真や動画を撮影します。気づいた点はメモにまとめておき、管理会社や大家さんに速やかに報告しましょう。
荷物搬入の際は、事前に決めておいたレイアウト通りに大型家具・家電を置いてもらうよう、明確に指示を出します。
- スマートフォンで日付がわかるように写真や動画を撮影します。気づいた点はメモにまとめておき、管理会社や大家さんに速やかに報告しましょう。
ライフラインの開通確認(電気・水道・ガスの開栓立ち会い)
- 電気
- 分電盤のブレーカーを上げる。
- 水道
- 室外のメーターボックスなどにある元栓を開ける。
- ガス
- 事前に予約した時間にガス会社の担当者による開栓作業に立ち会う。
まとめ

一人暮らしの引っ越しは、やることが多くて大変に感じるかもしれません。しかし、一つ一つのタスクは決して難しいものではありません。
この記事でご紹介したチェックリストを活用し、やるべきことを「見える化」して計画的に準備を進めることが、スムーズで快適な新生活への一番の近道です。手続きの漏れや直前の焦りをなくし、落ち着いて準備を進めていきましょう。
大変な準備を乗り越えた先には、自由で楽しい新生活が待っています。この記事が、あなたの素晴らしいスタートの一助となれば幸いです!










